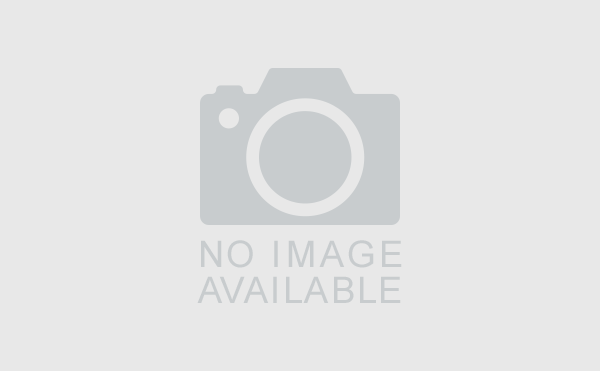理事長雑感⑤「合理的配慮」と権利の主体
障害者福祉や特別支援教育の分野において「合理的配慮」という用語は、もう耳慣れた言葉となっています。でも、一般の方の中には、合理的配慮に対して「ずるい」「わがまま」「甘え」というような誤解をしている方もいるようです。
さて、今回はこの「合理的配慮」(の訳)について考えてみましょう。国連の障害者権利条約「第二条 定義」において、「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されています。英文は、“Reasonable accommodation” means necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms;です。Reasonable accommodationは、素直に訳すならば、「合理的な調整」となります。
なぜ、これを「合理的配慮」という訳をしたのでしょうか?「配慮」という言葉は古くから日本語にあり、他者への思いやりや気配りを表現する言葉であり、類語としては「心配り」「心づくし」「心遣い」です。英語ならば「consideration」「concern」にあたる概念でしょう。本来の「調整」とは、かなりかけ離れた意味だと思いませんか。「合理的配慮」は、障害者からの申し出があれば、行政や企業は無理のない範囲での対応をしなければ差別とみなされます。つまり、障害者の当然な要求であり、申し出することは権利です。「配慮」という語は、社会(行政・企業等)が、障害者のことを思いやって調整をするというニュアンスになると思いませんか。だから、一部で「わがまま」とか「甘え」などという誤解を招いているのかもしれません。
障害者権利条約の日本語訳には、他にも気になる訳があります。第24条の「教育」2では「(b) 障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、障害者を包容し、質が高く、かつ、無償の初等教育を享受することができること及び中等教育を享受することができること。」と訳されていますが、英語では、(b) Persons with disabilities can access an inclusive, quality and free primary education and secondary education on an equal basis with others in the communities in which they live;となっています。「享受」は「受けいれて自分のものにする」こと、「恩恵に与ってそれを堪能する」ことを意味する語ですが、原文は「アクセスすることができる」つまり、「利用できる」「入手できる」となります。「享受」と「アクセス」では、主体に違いがあり、ニュアンスが異なると思われます。
外務省が訳した公定訳(日本語らしい表現・訳といえばそうかもしれませんが)、曖昧な訳・表現になっている感がします。障害者権利条約の原文・英文にあるように、「合理的配慮」を求める権利やインクルーシブな教育を受ける権利は、障害者の主体的な権利ですので、「甘え」などと思わず遠慮なく申し出ることが大切です。
(2025.8.17 記)