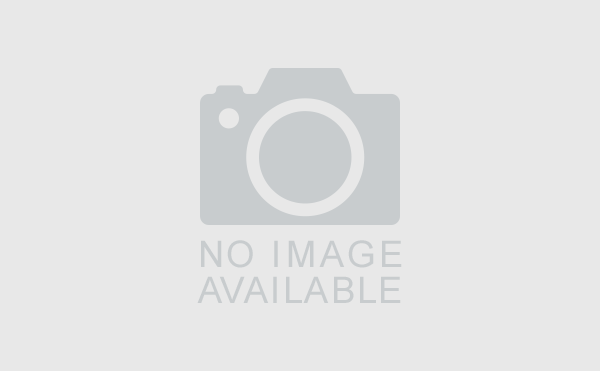理事長雑感⑦ 池田太郎先生と「民間ホーム」
このタイトルを見て、「池田太郎って誰?」あるいは「民間ホームって何だろう?」と思われる方が多いかもしれません。池田太郎(1908–1987)は、戦後まもなく糸賀一雄、田村一二とともに近江学園を創設し、その後、滋賀県立信楽学園の園長を務め、1962年に信楽青年寮を立ち上げた方です。数回しかお会いしていませんが、私にとって障害児教育の師の一人ともいえる存在です。そこで以下では「池田先生」と記します。そして「民間ホーム」とは、池田先生が信楽の地で実践した、現在のグループホームの原型ともいえる生活の場でした。
1980年の夏、当時大学院生だった私は、信楽青年寮を見学するために信楽を訪ねました。信楽は、草津線の貴生川駅から信楽高原鉄道(単線で、1991年には死者42名を出す衝突事故が起きています)で約25分の終点にある、陶芸の町として知られる山あいの地域です。当時は、知的障害のある人の一般就労率が全国一といわれていました。
池田先生は、たった一人の見学者である私を玄関で迎えてくださり、園長室で青年寮の概要を説明された後、自ら施設内を案内してくださいました。園生の仕事ぶりや作品について丁寧に紹介され、昼食までご一緒させていただきました。そのとき先生が語られた「食器は割れないアルミやプラスチックではなく、あえて割れる陶器を使っています」という言葉が、今も印象に残っています。見学のあとには「せっかくだから、園生が働いている会社や民間ホームも見ていくといいですね」と勧めてくださり、自ら地図を描いて見学先に電話までしてくださったのです。
民間ホームは、先生のご息女が世話人を務める、ごく普通の民家でした。青年寮で生活していた人たちが5人ほどで共同生活を送り、そこから職場へ通っていました。今のように設備が整っていたわけではありませんが、家庭的で温かな雰囲気に満ちていました。
1970年代当時、知的障害のある人の生活の場といえば、「大規模な入所施設」か「家庭での介護」しかなく、地域で暮らす仕組みはほとんど存在しませんでした。そうした時代に、池田先生が制度に先んじて「民間ホーム」を実践されたのは、「障害のある人も地域の中で、あたりまえに暮らしてほしい」という強い願いがあったからにほかなりません。この取り組みは、知的障害のある青年たちが親元を離れ、地域の中で働きながら暮らす拠点となり、のちの「障害者の地域生活支援」の流れに大きな影響を与えました。
あれから40年以上が経ちましたが、知的障害のある人の地域移行の仕組みは、いまだ十分とはいえません。池田先生の先駆的な実践を思い返すと、制度の遅れを残念に思うとともに、私たちに残された課題の大きさを改めて感じます。
最後になりますが、見学を終えて青年寮を後にするとき、私は持参していた池田先生の著書にサインをお願いしました。そこに記された言葉は「求道無限」。長く福祉の道を歩まれた先生が、これから障害児教育を志そうとしていた私に贈ってくださった言葉として、今も心の支えであり、私の座右の銘となっています。